本文
ことば調べコーナー
更新日:2022年3月31日更新
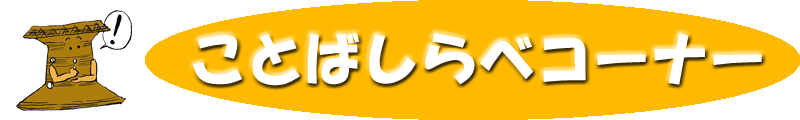
ことばしらべコーナー
| 50音 | ことばと読み | 説 明 |
|---|---|---|
| あ行 | 遺跡(いせき) | 昔の人が生活していた跡。 |
| 円筒埴輪 (えんとうはにわ) |
埴輪のうち、最も多く使われる筒形(つつがた)の埴輪。 |
|
| か行 | 回廊(かいろう) | 寺の主要な建物を囲む、またはつなげるように造られた廊下(ろうか)。 ・「備前国分寺・国分尼寺跡」 ・「美作国分寺・国分尼寺跡」 |
| 伽藍配置(がらんはいち) | 寺の塔や金堂、講堂といった建物の配置。時代によって変化します。 ・「幡多廃寺塔跡」 ・「備前国分寺・国分尼寺跡」 ・「備中国分寺・国分尼寺跡」 ・「美作国分寺・国分尼寺跡」 |
|
| 官衙(かんが)遺跡 | 古代の役所跡。国ごとの役所として国府(こくふ)、郡ごとの役所として郡衙(ぐんが)などがありました。 ・「陶馬」 |
|
| 基壇 (きだん) |
建物の土台となる高まり。まわりを石などで囲い、立派につくるものもあります。 ・「賞田廃寺跡」 ・「備前国分寺・国分尼寺跡」 ・「美作国分寺・国分尼寺跡」 ・「栢寺廃寺」 ・「熊山遺跡」 |
|
| 魏志倭人伝 (ぎしわじんでん) |
約1,700年前に中国にあった魏(ぎ)という国の歴史書です。この頃日本に「邪馬台国(やまたいこく)」という国があり、「卑弥呼(ひみこ)」という女王のいたことが書かれています。 ・「楯築遺跡」 |
|
| 国分寺(こくぶんじ)・ 国分尼寺(こくぶんにじ) | 「仏教の教えにより国をまもり、平和な世の中へ」との願いから、奈良時代の天平〈てんぴょう〉13(741)年、聖武天皇(しょうむてんのう)の命によって、全国60余国ごとに建てられたものです。 ・「備前国分寺・国分尼寺跡」 ・「備中国分寺・国分尼寺跡」 ・「美作国分寺・国分尼寺跡」 |
|
| 弧帯文 (こたいもん) |
特殊器台などに描かれた、平行する弧状の線からなる帯を組み合わせた文様。 ・「特殊器台・特殊壺」 |
|
| 古墳(こふん) |
古墳時代に盛んに造られたお墓。鍵穴の形をした前方後円墳、大きな四角と、小さな四角をくっつけたような形の前方後方墳、丸い形をした円墳、四角い形をした方墳などがあります。 |
|
| 講堂(こうどう) | お寺の中の建物の一つ。お経について教え、学ぶ建物。 ・「備前国分寺・国分尼寺跡」 ・「幡多廃寺塔跡」 ・「美作国分寺・国分尼寺跡」 |
|
| 金堂(こんどう) | 仏像をまつったお寺の中心となる建物。平安時代以降は本堂と呼ぶようになります。 ・「賞田廃寺跡」 ・「備前国分寺・国分尼寺跡」 ・「幡多廃寺塔跡」 ・「美作国分寺・国分尼寺跡」 |
|
| 金銅装(こんどうそう) | 銅に金メッキしたもの。古墳時代の大刀や馬具(ばぐ)などのかざりに使われました。 ・「装飾付大刀」 |
|
| さ行 | 心礎(しんそ) | 塔の中心に建てられる柱〔心柱(しんばしら)〕を支える礎石です。 ・「栢寺廃寺」 ・「幡多廃寺塔跡」 |
| 須恵器 (すえき) |
古墳(こふん)時代の中ごろに朝鮮半島から伝わったかたい土器。窯(かま)で高い温度で焼かれるため、灰色をしています。 ・「こうもり塚古墳」 ・「箭田大塚古墳」 ・「寒風古窯跡群」 ・「亀山焼」 ・「備前焼」 |
|
| 透かし孔 (すかしあな) |
土器や埴輪の表面に開けられた表面にあけられた△、□や○形などの穴。 ・「特殊器台・特殊壺」 |
|
| 青銅器 (せいどうき) |
銅とスズで作られた道具や器。日本では弥生時代以降に作られました。銅鐸(どうたく)や銅剣(どうけん)、銅矛(どうほこ)などが知られています。 ・「銅鐸」 |
|
| 石器(せっき) | 石を材料にした道具。打ち欠いてつくる打製石器(だせいせっき)とみがいて仕上げる磨製石器(ませいせっき)がある。 ・「鷲羽山遺跡」 ・「恩原遺跡群」 |
|
| 石棺(せっかん) |
石でつくった棺(ひつぎ)。古墳時代に主に用いられました。岡山県内では井原市周辺の石で作った石棺があることが知られています。 |
|
| 象嵌(ぞうがん) | 金属などの表面に細く浅い溝を掘り、別の材料をはめる技術。美しいかざりを描くことができます。古墳時代以降、刀や刀の部品などに使われることがあります。 ・「装飾付大刀」 |
|
| 礎石(そせき) | 建物の柱の台となる石。飛鳥時代ごろから、お寺や宮殿など、瓦葺き、あるいは大きな建物で使われるようになりました。 ・「鬼ノ城」 ・「備中国分寺・国分尼寺」 |
|
| た行 | 竪穴式石室(たてあなしきせきしつ) |
古墳時代前半に作られた死んだ人を収める石造りの部屋。通路は持たず、天井をかけることで密閉する構造。 |
| 竪穴住居(たてあなじゅうきょ) | 地面を掘りくぼめて、上に屋根をかけた半地下式の住居。 ・「百間川遺跡群」 ・「沼遺跡」 |
|
| 段築(だんちく) | 古墳をつくる方法で、墳丘の大きさを小さくしながら積み重ねていきます。 ・「作山古墳」 |
|
| 造り出し(つくりだし) |
前方後円墳や円墳などにつくられていることがある四角い高まり。まつりの場所だと考えられています。 |
|
| 塔(とう) | お寺の中にある建物の1つ。金堂とともに寺の中心となる重要な施設です。 ・「栢寺廃寺」 ・「賞田廃寺跡」 ・「幡多廃寺塔跡」 ・「備前国分寺・国分尼寺跡」 ・「美作国分寺・国分尼寺跡」 |
|
| 陶棺(とうかん) | 子どもホームページ「陶棺」をごらんください。 | |
| は行 | 埴輪(はにわ) |
古墳に置かれた焼き物。円筒形(えんとうがた)のほか、盾(たて)やよろい、人や動物をかたどったものが知られています。 |
| 鳳凰(ほうおう) | 中国の伝説上の鳥。クジャクに似た美しい鳥だと言われています。日本では刀のかざりのモデルになるほか、お寺の屋根のかざりとしても使われます。 ・「こうもり塚古墳」 ・「装飾付大刀」 |
|
| 掘立柱建物(ほったてばしらたてもの) | 地面に穴を掘って柱を立てた建物。 ・「津島遺跡」 |
|
| ま行 | 木棺(もっかん) | 木でつくった棺(ひつぎ)。弥生時代以降、よく使われるようになります。大きな木を2つに割って作ったり、板を組み合わせて作ったりしました。 ・「こうもり塚古墳」 ・「四ツ塚古墳群」 |
| ら行 | 龍(りゅう) | 中国の伝説上の動物。角は鹿(しか)、頭はらくだ、体はへび、爪は鷹(たか)、手は虎(とら)、耳は牛にと、いろいろな動物の特ちょうをあわせ持つとされます。日本では土器に描かれたり、刀かざりのモデルになったりします。 ・「装飾付大刀」 |
| や行 | 横穴式石室 (よこあなしきせきしつ) |
古墳時代後半に作られた死んだ人を収める石造りの部屋。通路と奥(おく)の遺体(いたい)を埋葬(まいそう)する部屋からなり、何人かいっしょに葬(ほうむ)られることが多い。 ・「四ツ塚古墳群」 ・「こうもり塚古墳」 ・「箭田大塚古墳」 ・「牟佐大塚古墳」 ・「大谷・定古墳群」 |


