本文
高間熊野神社の森(たかまくまのじんじゃのもり)
ガイド
社伝によると、熊野神社は土御門天皇の勧請で建仁元年(1201)「天王宮」と称し、延宝元年(1673)に造立され、後に熊野神社として改称したもので、地域の鎮守の神様として親しまれています。
社叢は、タブノキ、モミ、ウラジロガシなどの高木層、カゴノキ、ヤブツバキなどの亜高木層、ヤブツバキ、ヤブニッケイなどの低木層により構成されています。
また、周辺の雑木林には、タブノキ、ヤブツバキ、カゴノキの巨樹が点在しています。特に沿岸地に多い樹種であるタブノキは海抜面からは分布の上限に近く、この健全な状況は学術的にも注目されるものです。
社叢は、タブノキ、モミ、ウラジロガシなどの高木層、カゴノキ、ヤブツバキなどの亜高木層、ヤブツバキ、ヤブニッケイなどの低木層により構成されています。
また、周辺の雑木林には、タブノキ、ヤブツバキ、カゴノキの巨樹が点在しています。特に沿岸地に多い樹種であるタブノキは海抜面からは分布の上限に近く、この健全な状況は学術的にも注目されるものです。



所在地
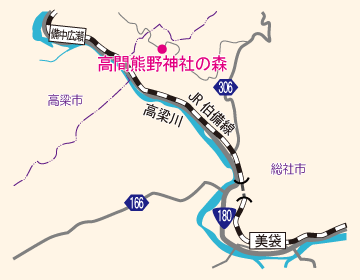
総社市種井
アクセス
JR伯備線備中広瀬駅から車30分
