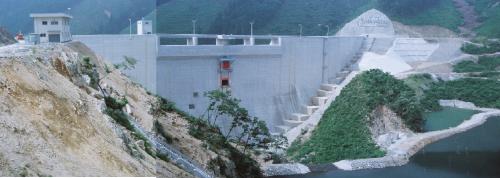本文
高瀬川ダム
◆ 高瀬川ダムの概要及びダム建設の背景 ◆

高瀬川ダム建設前の高梁川下流部においては、大正年間に内務省直轄で改修工事が完成していたため、昭和9年の室戸台風や昭和20年の枕崎台風等にも十分対処できましたが、高梁川の上流部から中流部にかけては、河川改修等が遅れていたため、昭和47年7月の豪雨では近年まれにみる大出水となり、その被害は死者1名、家屋全半壊61戸、浸水家屋1,572戸、流失田畑84ha、国鉄伯備線においては1ヶ月間の不通といった甚大な被害がもたらされました。
このため西川及び高梁川治水計画の一環として、洪水被害の軽減等を目的に高瀬川ダムが建設されました。
高瀬川ダムの役割
洪水調節
ダム地点の計画高水流量240m3/秒のうち、210m3/秒の洪水調節を行い、下流流域への洪水被害の軽減を図ります。
既得取水の安定化及び河川環境の保全
ダム下流の河川用水の補給、水質、動植物の生息等河川環境の保全などのために、既得取水の安定化及び河川環境の保全を図ります。
水道用水
水道用水として日量80,000m3を供給します。
発電
ダムの放流水を利用して最大出力280キロワットの発電を行います。
高瀬川ダムの諸元
|
ダ ム 及 び 貯 水 池 諸 元 |
|
||||||
|
|
河 川 名 |
高梁川水系西川支川高瀬川 |
放流設備 |
|
|||
|
|
位置 |
左岸 |
新見市神郷釜村 |
非常用洪水吐 |
巾11.5m×高2.8m 2門 |
|
|
|
|
右岸 |
新見市神郷釜村 |
巾13.5m×高2.8m 2門 |
|
|||
|
|
調 査 |
昭和48年度から50年度 |
常用洪水吐 |
φ1.95m×1門 |
|
||
|
|
建 設 |
昭和51年度から56年度 |
利水放流設備 |
ジェットフローゲート |
|
||
|
|
ダ ム |
φ400mm×1門 |
|
||||
|
|
ダム名 |
高瀬川ダム |
選択取水設備 |
1号取水管 φ400mm |
|
||
|
|
型式 |
重力式コンクリートダム |
2号取水管 φ400mm |
|
|||
|
|
堤高 |
67.0m |
3号取水管 φ800mm |
|
|||
|
|
堤頂長 |
273.6m |
貯 水 池 |
|
|||
|
|
堤体積(減勢工含む) |
188,000m3 |
集水面積 |
21.6km2 |
|
||
|
|
天端標高 |
標高494.50m |
湛水面積 |
0.28km2 |
|
||
|
|
越流部標高 |
標高490.70m |
総貯水容量 |
4,530,000m3 |
|
||
|
|
法勾配 |
上流面 |
標高461.00以上 |
垂直 |
有効貯水容量 |
4,080,000m3 |
|
|
|
標高461.00以下 |
1対0.35 |
洪水調節容量 |
3,500,000m3 |
|
||
|
|
下流面 |
1対0.75 |
利水容量 |
580,000m3 |
|
||
|
|
ダムサイト地質 |
流紋岩 |
堆砂容量 |
450,000m3 |
|
||
|
|
計 画 概 要 |
設計洪水位 |
標高493.50m 標高490.70m |
|
|||
|
|
設計洪水量 |
520m3/s |
(サーチャージ水位) |
|
|||
|
|
計画高水流量 |
240m3/s |
常時満水位 |
標高469.70m |
|
||
|
|
最大放流量 |
30m3/s(最大50m3/s) |
計画堆砂位 |
標高461.00m |
|
||
|
|
管理用発電設備 |
横軸フランシス水車 |
|
|
|
||
|
|
発電最大出力 |
280キロワット |
|
|
|
||
高瀬川ダム建設のあゆみ
昭和51年度 ダム本体工事に着手
昭和56年度 ダム竣工
昭和57年度 ダム運用開始
高瀬川ダム建設写真
 |  |  |
|---|---|---|
建設前 | 建設中 | 建設中 |
| ||
完成 | ||
高瀬川ダム周辺のイベント情報
施設内には、オートキャンプ場、神郷温泉、交流山村体験館、多目的広場、全天候方ゲートボール場&テニスコート、ふれあい交流広場等があります。
・しんごう湖畔マラソン(主催:新見市しんごう湖畔マラソン大会実行委員会)
開催時期 11月上旬
会場:グリーンミュージアム神郷及び周辺
・デュアスロンinしんごう(主催:神郷デュアスロン実行委員会、岡山県トライアスロン協会)
開催時期 10月上旬
会場:グリーンミュージアム神郷及び周辺
高瀬川ダムの位置
住所 新見市神郷釜村634