本文
不当要求防止責任者・不当要求防止責任者講習
不当要求防止責任者の選任と講習
不当要求防止責任者講習とは
最近の暴力団は、飲食店などからのみかじめ料や用心棒料など昔ながらの資金獲得だけでなく、民事問題や経済取引に深く介入し、一般市民や企業、あるいは行政機関などから不当な利益を得ようと不当な要求を繰り返すなど、その資金獲得活動の範囲を拡大しています。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という)では、暴力団からの不当な要求による被害を防止するために、公安委員会が事業者の皆さんが選任した「不当要求防止責任者」に対し、不当要求に対する対応方法などについて、各種資料の提供や、指導・助言などの援助を行うことを定めています。
この援助の一つに「不当要求防止責任者講習制度」があります。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という)では、暴力団からの不当な要求による被害を防止するために、公安委員会が事業者の皆さんが選任した「不当要求防止責任者」に対し、不当要求に対する対応方法などについて、各種資料の提供や、指導・助言などの援助を行うことを定めています。
この援助の一つに「不当要求防止責任者講習制度」があります。
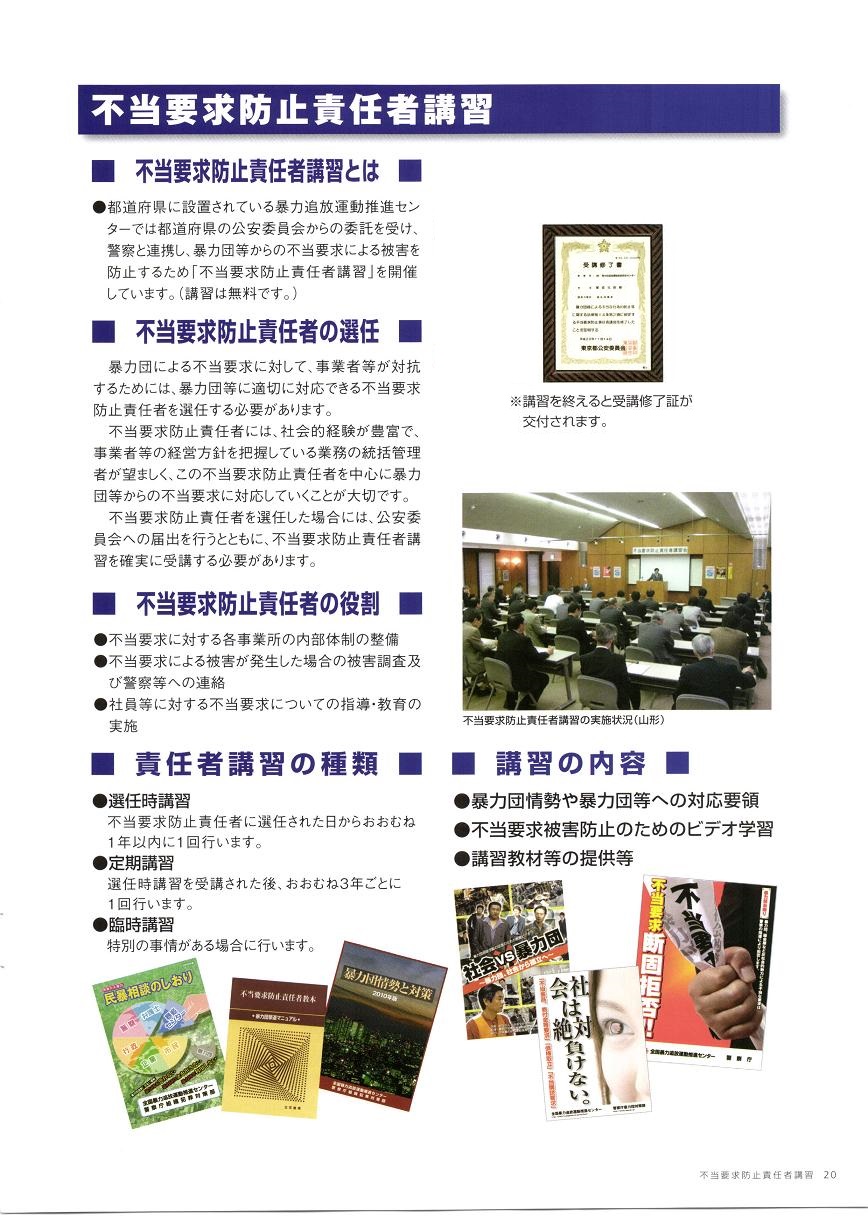
不当要求防止責任者講習に関するQ&A
Q1 不当要求防止責任者の仕事はどのようなものですか。
A 暴力団対策法で「不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務」とされていますが、具体的には次のような業務です。
(1) 事業所における対応体制の整備に関する業務
(2) 従業員に対する指導教養の実施に関する業務
(3) 不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務
(4) 暴力団排除組織との連絡に関する業務
(5) その他の不当要求による被害を防止するための業務
Q2 不当要求防止責任者を選任する事業所の範囲は
A 個人事業、民間事業、公益法人、協同組合等従業員を雇用している事業所であれば、事業の規模は問いません。
責任者の選任及び選任後の講習会出席は義務ではありませんが、銀行などの金融業・建設業・不動産業・風俗営業などのように暴力団等からの不当要求を受けやすい業種の事業所は、責任者の選任及び選任後の講習会受講を推奨します。
責任者は、事業所、営業所ごとに原則として一人選任するのが適当ですが、複数になってもかまいません。
Q3 どのような人が責任者になればよいのでしょうか
A 責任者としての資格などはありませんが、暴力団対策法で「事業にかかる業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者」と規定されていることから、例えば「総務課長」または「総務係長」等を選任するのがベストです。支店が複数ある会社であれば、各支店で統一されることを推奨します。また、おおむね3年に一度の講習会に出席可能な方でお願いします。
Q4 選任の手続きが面倒ではないですか
A 簡単な手続きです。
このホームページに掲載の責任者選任届出書に必要事項を書いて所在地を管轄する警察署へ提出するだけで結構です。(警察本部(組織犯罪対策第一課)では受付していません。)
届出書の提出は、所在地を管轄する警察署刑事課(刑事第二課)窓口へ本人または代理人が持参のうえ提出してください。(郵送は不可としています。窓口で社員証等によって、身分確認させて頂く場合があります。)
なお、届出書は先述の各警察署の窓口にありますので、窓口で記載のうえ、そのまま提出することもできます。
お問い合わせは、組織犯罪対策第一課 講習担当まで Tel086-234-0110(内線4463)(土・日等閉庁日を除く、午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分まで)
A 暴力団対策法で「不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務」とされていますが、具体的には次のような業務です。
(1) 事業所における対応体制の整備に関する業務
(2) 従業員に対する指導教養の実施に関する業務
(3) 不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務
(4) 暴力団排除組織との連絡に関する業務
(5) その他の不当要求による被害を防止するための業務
Q2 不当要求防止責任者を選任する事業所の範囲は
A 個人事業、民間事業、公益法人、協同組合等従業員を雇用している事業所であれば、事業の規模は問いません。
責任者の選任及び選任後の講習会出席は義務ではありませんが、銀行などの金融業・建設業・不動産業・風俗営業などのように暴力団等からの不当要求を受けやすい業種の事業所は、責任者の選任及び選任後の講習会受講を推奨します。
責任者は、事業所、営業所ごとに原則として一人選任するのが適当ですが、複数になってもかまいません。
Q3 どのような人が責任者になればよいのでしょうか
A 責任者としての資格などはありませんが、暴力団対策法で「事業にかかる業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者」と規定されていることから、例えば「総務課長」または「総務係長」等を選任するのがベストです。支店が複数ある会社であれば、各支店で統一されることを推奨します。また、おおむね3年に一度の講習会に出席可能な方でお願いします。
Q4 選任の手続きが面倒ではないですか
A 簡単な手続きです。
このホームページに掲載の責任者選任届出書に必要事項を書いて所在地を管轄する警察署へ提出するだけで結構です。(警察本部(組織犯罪対策第一課)では受付していません。)
届出書の提出は、所在地を管轄する警察署刑事課(刑事第二課)窓口へ本人または代理人が持参のうえ提出してください。(郵送は不可としています。窓口で社員証等によって、身分確認させて頂く場合があります。)
なお、届出書は先述の各警察署の窓口にありますので、窓口で記載のうえ、そのまま提出することもできます。
お問い合わせは、組織犯罪対策第一課 講習担当まで Tel086-234-0110(内線4463)(土・日等閉庁日を除く、午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分まで)
Q5 責任者講習はどのような内容ですか。
A 講習は、岡山県公安委員会からの委託により、暴追センターが行っています。
講習は、選任された不当要求防止責任者が、業務を行う上で必要な知識や技能を習得するためのもので、新規に選任された責任者を対象に行われる「選任時講習」と、概ね3年に一度行われる定期講習などがあります。
具体的な講習の内容は、
(1) 暴力団の活動実態
(2) 不当要求の手口
(3) 不当要求に対する対応要領
などで、最新の暴力団情勢に基づいて講習を行っています。
講習終了後、岡山県公安委員会から受講修了書が交付されます。
なお、受講案内があった場合、受講は義務ではありませんが、受講されることを推奨します。
Q6 責任者講習の受講は無料ですか
A 講習は無料です。(講習に必要な教材も無償で配布します。)
Q7 その他
・ 岡山県公安委員会からの講習案内に基づく、事前の受講にかかる申し込みが必要です。
・ 新規(選任時)対象の方は、届出の時期によって、次年度に案内される場合があります。
・ 定期対象の方の受講案内時期は、他府県の受講歴も考慮しています。
・ 責任者選任届出書を提出されている責任者が受講対象となりますので、責任者が変更された場合、後任の方は、すみやかに責任者選任届出書の提出をお願いします。
・ 受講日(受講会場)の振り替えは可能ですが、予定されている受講対象者の申し込み状況等によってはご希望に沿えない場合がありますので、開催日の概ね一か月前までには、その旨の連絡をお願います。
・ 受講歴にかかわらず早期受講を希望される方は、責任者選任届出書の提出時に窓口でその旨を申し出てください。ただし、受講間隔が短い場合、同じ内容の受講となる場合があります。
A 講習は、岡山県公安委員会からの委託により、暴追センターが行っています。
講習は、選任された不当要求防止責任者が、業務を行う上で必要な知識や技能を習得するためのもので、新規に選任された責任者を対象に行われる「選任時講習」と、概ね3年に一度行われる定期講習などがあります。
具体的な講習の内容は、
(1) 暴力団の活動実態
(2) 不当要求の手口
(3) 不当要求に対する対応要領
などで、最新の暴力団情勢に基づいて講習を行っています。
講習終了後、岡山県公安委員会から受講修了書が交付されます。
なお、受講案内があった場合、受講は義務ではありませんが、受講されることを推奨します。
Q6 責任者講習の受講は無料ですか
A 講習は無料です。(講習に必要な教材も無償で配布します。)
Q7 その他
・ 岡山県公安委員会からの講習案内に基づく、事前の受講にかかる申し込みが必要です。
・ 新規(選任時)対象の方は、届出の時期によって、次年度に案内される場合があります。
・ 定期対象の方の受講案内時期は、他府県の受講歴も考慮しています。
・ 責任者選任届出書を提出されている責任者が受講対象となりますので、責任者が変更された場合、後任の方は、すみやかに責任者選任届出書の提出をお願いします。
・ 受講日(受講会場)の振り替えは可能ですが、予定されている受講対象者の申し込み状況等によってはご希望に沿えない場合がありますので、開催日の概ね一か月前までには、その旨の連絡をお願います。
・ 受講歴にかかわらず早期受講を希望される方は、責任者選任届出書の提出時に窓口でその旨を申し出てください。ただし、受講間隔が短い場合、同じ内容の受講となる場合があります。

